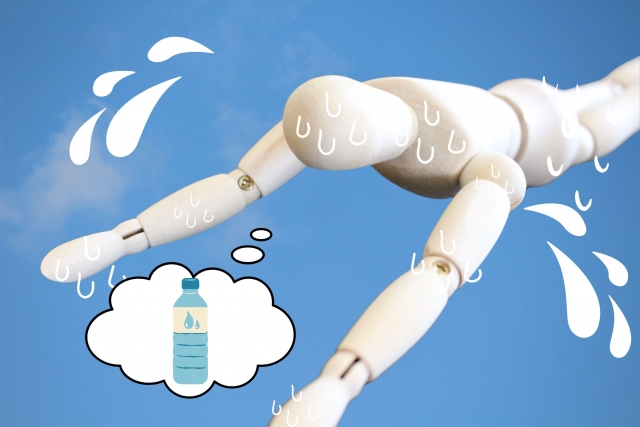近年の気温上昇により、熱中症の問題は年々深刻化しています。特に、梅雨から厳しい暑さが落ち着くまでの期間に、アスリートに多い『労作性(ろうさせい)熱中症対策』についてお話します。
■労作性熱中症とは?
熱中症には、大きく分けて労作性熱中症と、非労作性熱中症の2種類があります。自宅の中等の日常生活で発症する『非労作性(ひろうさせい)熱中症』と、スポーツや仕事中の環境で発症する『労作性熱中症』の2つです。
熱中症は、湿度や気温が高いと発症する症状と思われていますが、原因は気候だけではありません。原因は大きく3種類あります。まずは、気温や湿度が高かったり、自然の風が弱かったりする「環境」です。室内でのパフォーマンス中でも、熱中症になる可能性は十分にあります。
強い日差しを受け続ける環境の場合、地面からの熱と、頭の上から日光を同時に受けることで熱中量になりやすいです。特に大人より身長が低い子どもは、地面からの照り返しを大人以上に強く受けることを忘れないでください。
2つ目の要因は「行動」です。寝不足や肥満も、脱水状態や体調不良の原因になります。500mlのスポーツドリンクに含まれる糖分は、角砂糖5個以上、炭酸飲料では、最高16個分にもなります。果汁100%でも濃縮還元の飲料は、風味と甘味のために、砂糖が使われることもあります。
甘みのある清涼飲料を飲み過ぎると、体がだるくなったり、脳がイライラしやすくなったり、さらにのどがかわきやすくなります。また、すぐに飲みたくなる中毒性があるだけでなく、基本的には大人が飲むことを想定した飲み物なので、糖分が多くなってしまいます。
だからといって、常に水で薄めると、ミネラルも塩分も十分に補給できないのでおすすめできません。軽い運動や室内でのトレーニング中は、麦茶やお水にして、清涼飲料水の飲み過ぎを防ぎましょう。
そして、最後の要因は「状況」です。体力を一気に使うパフォーマンスは、体内に異常な量の熱が生まれて、熱中症リスクが高まります。指導者や親御さんが子供だった頃とは、気温も湿度も明らかに違っていることを忘れないでください。
ジュニアアスリートに多いのは、軽度な症状から順に、パフォーマンスを終えた瞬間にめまいや立ちくらみでふらつく『熱失神』、足がつる『運動誘発性筋けいれん』、強い疲労感や頭痛、異常に興奮状態になってしまうことで、パフォーマンスの継続が難しくなる『熱疲労』です。
さらに、重度の場合、体温が40度以上になり、嘔吐や意識が不安定になる『労作性熱射病』は命の危険を伴います。足がつったり、異常に汗が多かったりすると思ったら、本人から体調不良の訴えがなくても、周りが迷わず休ませてください。
■労作性熱中症を防ぐ効果的な体の冷やし方
体の冷やし方には『外部冷却』と『内部冷却』の2種類があります。労作性熱中症を予防するには、この両方で、効率よく冷やすのが理想的です。特に、気温も湿度も高い環境のプロのアスリートは、この2種類の冷却を同時に実践して、皮膚の温度と深部体温の上昇を防いでいます。
皮膚の温度をすぐに下げられるのが、外部冷却で、熱中症をとりあえず防ぐ対策として、まず最初に行いたい冷やし方です。冷たさを一番感じやすいのはおでこで、他には、胸や前腕から冷やしてください。
熱中症の判断基準になる深部体温を下げるには、内部冷却と同時に行うのが効果的です。内部冷却は体を深部、いわゆる内側から冷やします。そこで、今注目されて多くのプロのアスリートも実践しているのが『アイススラリー』です。
アイススラリーとは、小さな粒上の氷を飲むことで、体を表面ではなく、内側の芯から冷やすことです。液体状の冷たい飲料を飲むよりも、氷を溶かすために熱を使うので、体の内側から効率的に熱を排出できる方法です。
スムージーをイメージしてみてください。さらさらの飲料よりも、体の中をゆっくり通るので、内臓に冷たい水分が長い時間あるため、深部体温をしっかり下げられます。スーパー等の、鮮魚の鮮度を保つために使われるフレーク状の氷のことなので、自作も可能です。
作り方は、ビニール袋に、フレーク状の氷と塩、レモンやオレンジなどのかんきつ類の果汁を入れて、平らにしてから3cm程度の厚みになるように並べたら、袋の中の空気をできるだけ抜き、口の部分をねじればできあがりです。
果汁を入れるなら氷の量の4分の1、塩はほんの少しで、甘ったるくならないようにしてください。凍らせて砕いたスポーツドリンクも効果的です。トレーニングや試合前に、口に入れて溶かさずそのまま飲み込みます。活動30分前に飲んで、深部体温を下げ始めるのが理想的です。
■トレーニングや試合の日の理想的な水分補給
水分は、パフォーマンス直前に飲むと胃が重くなるので、練習の30分前までにしっかり摂取します。運動中には、1回200ml程度を、15分から30分を目安に飲みます。200mlの目安は、だいたい10口分(10回飲み込む)と覚えておけば良いでしょう。
最後に、上白糖よりもミネラルが豊富で、苦みやクセがない薄い茶色のきび糖を使った、優しい甘みの手作り飲料をご紹介しておきます。さとうきびの風味で苦みやクセがなく、甘ったるくなりません。
作り方は、冷たい水500mlに対して、天然塩1g、きび糖20gを入れてよく振って溶かします。水と氷の合計で500mlで作るのもおすすめです。きび砂糖は、できあがるまでの手間がかかるので普通のお砂糖よりは少し値段は高くなります。
それでも、お料理に照りやコクが出て風味が高まり、色味が濃くなるので、見た目で食欲を増しやすくなります。これは、近年のジュニアアスリートの世代で、しっかり噛まないといけないお料理にストレスを覚える子に効果的です。
きび糖は、肉をやわらかくしたり、魚の生臭さを消したりしてくれるので、肉や魚の摂取量が少ない時に、無理せず増やすことが期待できるので、ぜひ購入し、手作りきび糖ドリンクに挑戦してみてください。
いかがでしたか。今回は、まだまだ暑さが続く夏に注意しなければならない労作性熱中症と、その対策について解説しました。参考にしてみてください。